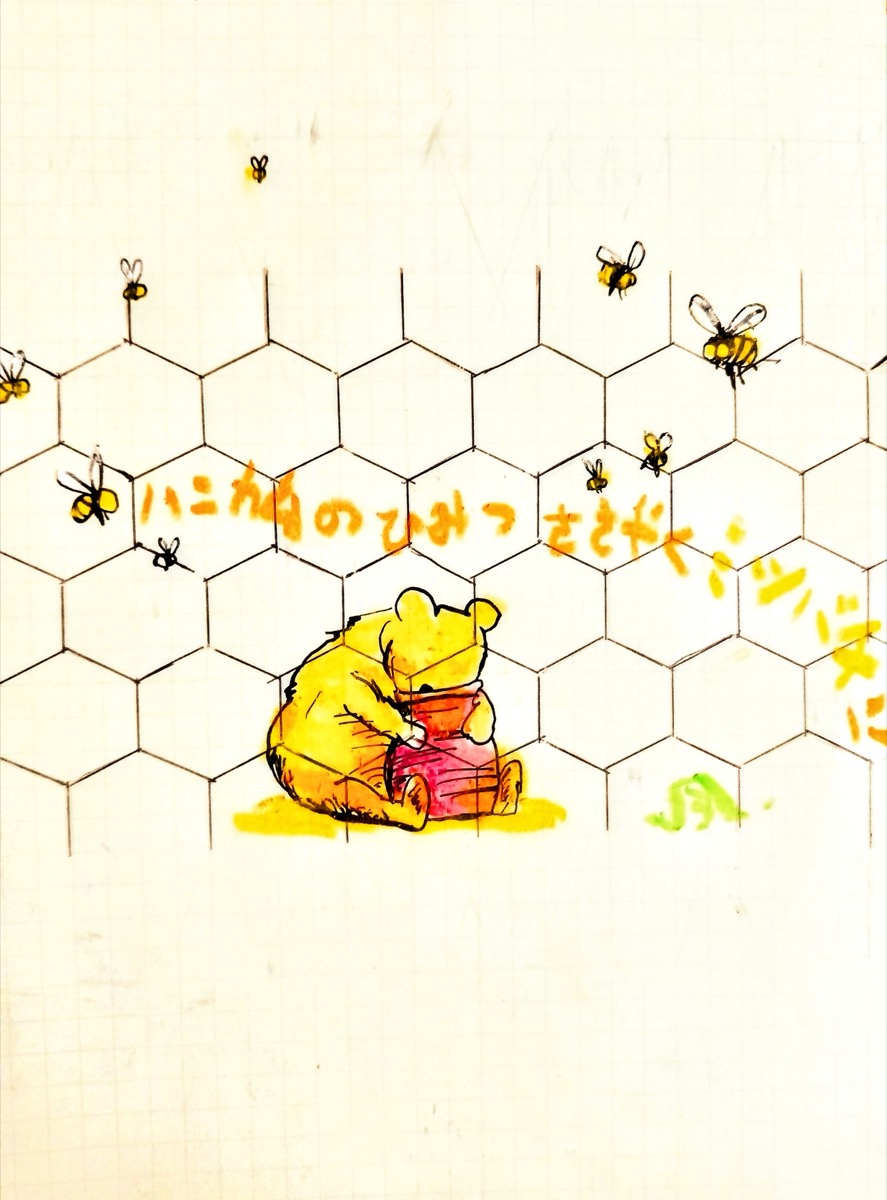 1978年、蜂の大群が人を襲う『スウォーム』なる映画があった。今回調べてみて初めて知ったが、これ『ポセイドン・アドベンチャー』や、『タワーリグインフェルノ』のアーウィン・アレン監督の、大スター総登場シリーズの一つだった!確かにヘンリー・フォンダやマイケル・ケインが出ていた(ただ、興行的にはコケた)。実はこの頃、映画界ではアリが、バッタが、ミミズが…大挙して人類に暇なく襲いかかっていた…。あの有名なアルフレッド・ヒッチコックの『鳥』に続けとばかりに。
1978年、蜂の大群が人を襲う『スウォーム』なる映画があった。今回調べてみて初めて知ったが、これ『ポセイドン・アドベンチャー』や、『タワーリグインフェルノ』のアーウィン・アレン監督の、大スター総登場シリーズの一つだった!確かにヘンリー・フォンダやマイケル・ケインが出ていた(ただ、興行的にはコケた)。実はこの頃、映画界ではアリが、バッタが、ミミズが…大挙して人類に暇なく襲いかかっていた…。あの有名なアルフレッド・ヒッチコックの『鳥』に続けとばかりに。
「はち」の語源は、巣が「はちす(蓮)」に似ているという説、また「刺す」の古語「はす」から等と言われる。また、漢字の「夆」は「群がる」の意で前述の映画のタイトル『swarm』と同じである。熟語の「蜂起」にもそんなイメージがある。刺す事については、実は針で人を刺す種はほんの一握り。また、針があるのは、それが産卵管から成る事からも分かるように、メスだけである。一匹が刺すと攻撃フェロモンが発せられ、集団で襲いかかる…!
そんな恐ろしい生物であるハチだが、蜂蜜で人類とは古くから結びついている。既に紀元前6000年頃のスペイン・アラーニャの洞窟に、蜂蜜を採る女性が描かれている。古代エジプト文明の壁画にも、燻製器で蜜を採取している様子が。メソポタミア文明でも、ミツバチを飼い慣らして、蜂蜜を採っている壁画が。クレタ島の遺跡からは、巣箱が金の装飾品と共に出土。マヤでも、ミツバチは地の中心で生まれ、火山の火の粉そっくりの姿。人間を無知から目覚めせるために、地上に遣わされたと考えられた。2025年、オックスフォード大学は、イタリア南部エストゥムの2500年前の地下神殿から発掘された青銅の壺に残された物質が、ハチミツだったと発表した。
ヒポクラテスは、蜂蜜は万民に良く、痛みに効くと記している。また、中世ヨーロッパでは、蜂蜜は日焼けや、咳・消化不良の薬、また蜂蜜酒の原料、何よりキャンドルを作る蜜蝋として重宝され、修道院には多くの巣箱が設置された。実際、ハチミツの抗菌力は非常に高く、腐ることは無い。殺菌・防腐作用に優れ、チフス菌・赤痢菌などは蜂蜜の中で生きられない。しかし、ティースプーン1杯の蜂蜜を産生するのに、一匹のハチの一生分が必要と聞くと、有り難いような、申し訳ないような…。
『ギリシャ神話』では、地母神デーメーテールが、「穢れなき母なるミツバチ」として崇拝されている。またゼウスは子供時代、クレタ島の洞窟で、ニンフのメリッサ達に、蜂蜜とヤギの乳で育てられた。洞窟も、火のように熱いミツバチに守られていた。アポローンとキュレーネーの息子アリスタイオスは、養蜂の神。銀梅花のニンフ達から、養蜂や、チーズの製法、オリーブの栽培も学んだ。
『ケルト神話』では、ハチは現世と天上界を結ぶ存在とされ、中世ヨーロッパでは家族の大事をハチに知らせるtelling the beesという風習があった。一家の首長がこれを行い、家族が死亡した時には、喪章の付いた黒布を巣箱に被せ、結婚の時には巣箱も飾り、その前にウェディングケーキを供えたという。
『旧約聖書』の『出エジプト』でも、約束の地カナンは、「乳と蜜の流れる地」と書かれている。
妖怪では、1691年に書かれた地誌『作陽誌』に蜂王が載る。一丈(約3m)の巨体、残忍な性格で、峠を通る人に様々な害をなし、生き血を吸っていた。旅の僧侶に、経文を書いた木偶人形で退治された。人形ともども蜂王を埋めたその地は、〈人形峠〉と名付けられた。また、奈良〈三日月堂〉に祀られる金剛執神は、蜂の宮と呼ばれる。〈平将門の乱〉の折り、像の石錺が蜂と化し、戦場の平将門に襲いかかり、殺したとも言う。
現代におけるハチのミステリーもある。1950年、ブラジルのハチ専門の科学者ワーウィック・カーは、品種改良により凶悪なアフリカナイズドミツバチ、通称キラービーを生み出した。捕食者であるラーテルに抵抗する為に凶暴化したアフリカミツバチと、セイヨウミツバチの交配により生みだされた。そのキラービー26匹が研究所を逃げ出し、中央アメリカからメキシコ、アメリカ南西部にまで広まってしまった…。そして、10年後にパニックが起こった。これは、当時のブラジルの軍事独裁政権が、カーをマッドサイエンティストとして批判する為、キラービーを利用した事が原因。実際、キラービーの危険性は低く、交配が進むことにより、温厚化している。
もう一つ、こちらは記憶に新しいが2006年、アメリカでセイヨウミツバチが大量に消失する現象が発生。〈蜂群崩壊症候群〉と呼ばれた。アメリカ各地で発生し、その数は四分の一にまで減少。同様な症例が、ヨーロッパ、台湾、日本でも発生。原因は未だ解明されていない…。
さて、描いたのは、ご存知英国のA・A・ミルンの『くまのプーさん』と、〈ハニカム構造〉。正六角形を隙間なく並べた構造で、蜂の巣・昆虫の複眼・亀の甲羅等に見られる。強度が高く、熱伝導性・導電性・衝撃吸収・断熱…に優れ、航空機・新幹線(〈500系〉・〈N700系〉)・F1マシーンのモノコック・戦車・デジカメ・サッカーゴール(ゴールが決まった際の見かけの良さ)にまで利用されている!〈宇宙エレベーター〉に使われる〈カーボンナノチューブ〉には原子レベルで使用。古くは、アメリカ初の有人宇宙船〈マーキュリー〉にも。近年では、あの〈ハヤブサ2〉の〈軽量高利得平面アンテナ〉にも使用された。筆者も、地方を巡回した展示の際に、実際に目にした。余談だが、〈ハヤブサ2〉の行った〈小惑星リュウグウ〉には、筆者とかみさんの名前も入ったマクロチップが今も眠っている…はず。
最後に…〈蜂群崩壊症候群〉を描いた2008年のナイト・シャマラン監督『ハプニング』より。『もし地球上からミツバチが消え去ったら、人類は4年も生きていけないでしょう。(アルバート・アインシュタイン)』ただ、これ、アインシュタインが言ったというのは、さすがに都市伝説らしい…。しかし、実際〈国連環境計画〉によれば、世界の食糧の9割を占める100種類の作物の内、7割はハチが受粉を媒介している…。
ハニカムのひみつをささやくミツバチに風来松